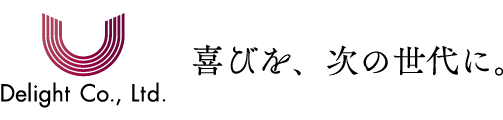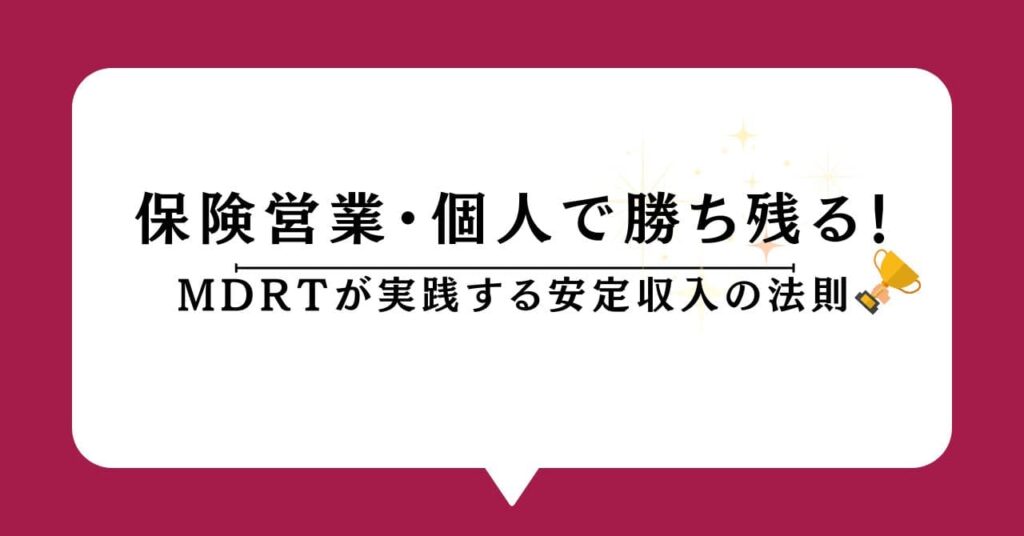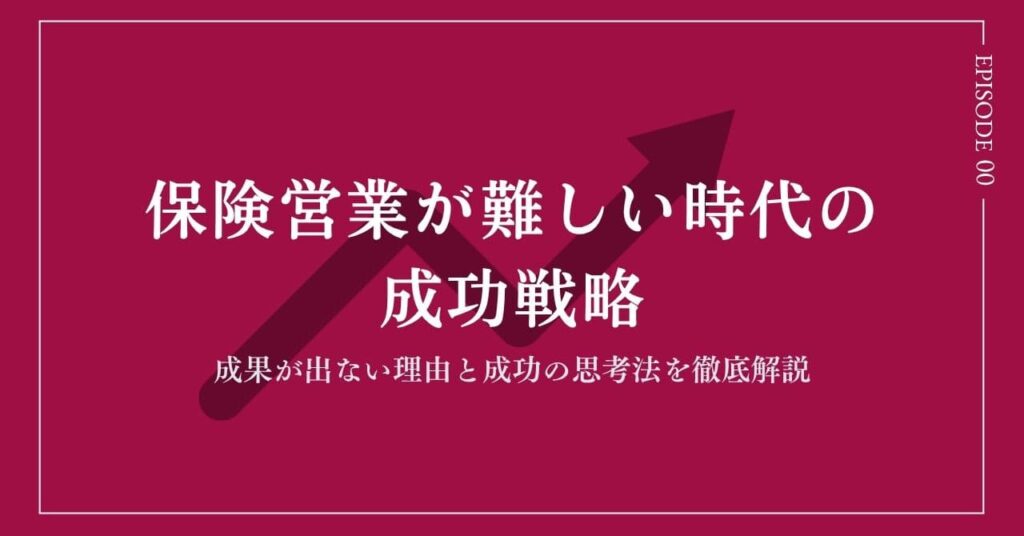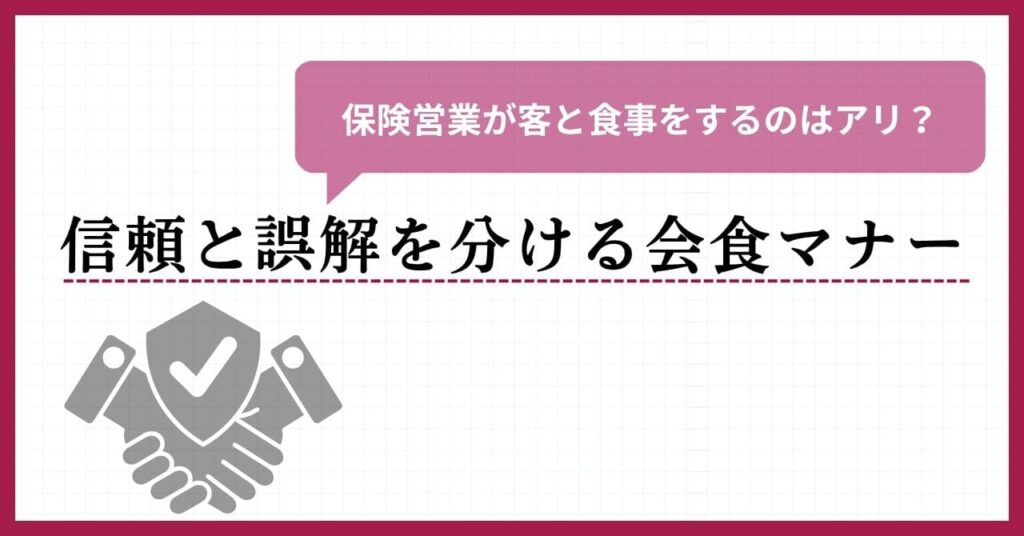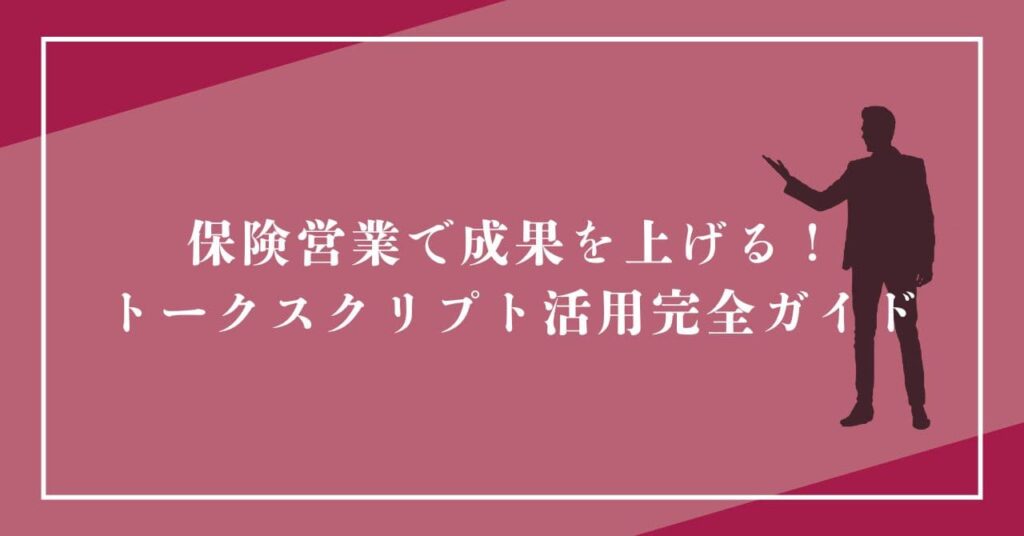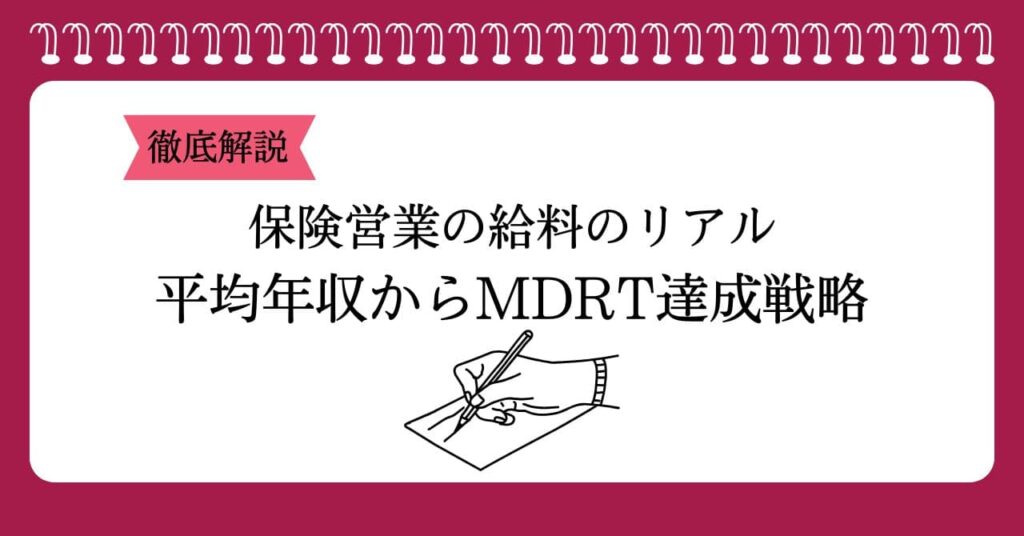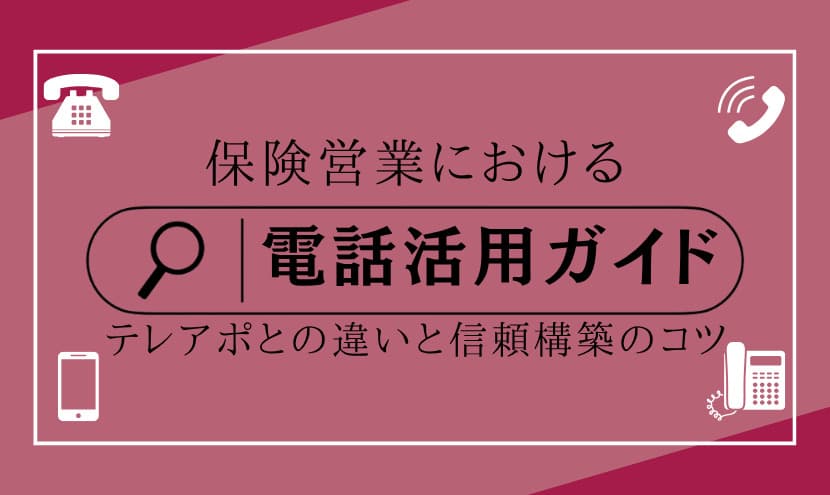保険営業における電話活用ガイド【テレアポとの違いと信頼構築のコツ】
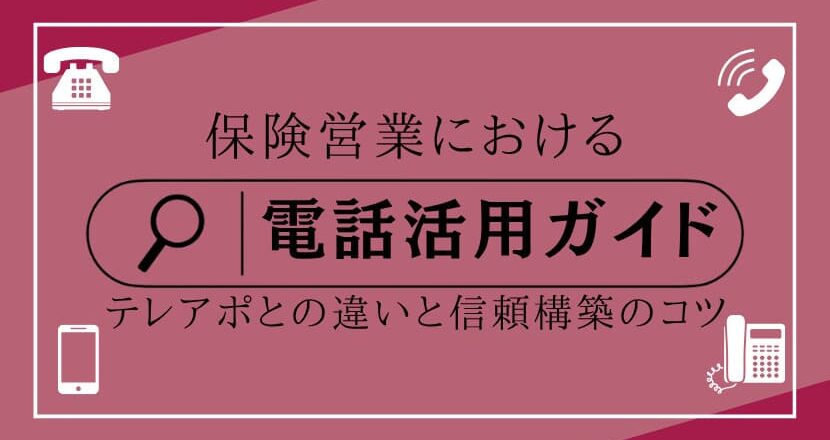
保険営業で「電話」と聞くと、いまだに“テレアポ=新規勧誘”というイメージを抱く人が多いのではないでしょうか。
しかし実際には、無作為なテレアポは法令で厳しく制限されており、効果も限定的です。
本当に成果を上げている営業マンは、電話を「信頼を築くためのフォロー・紹介獲得のツール」として活用しています。
本記事では、金融庁ガイドラインや保険業法を踏まえつつ、既存・紹介顧客との電話で成果を生むための具体的トーク設計・フォロー戦略・NG対応までを徹底解説します。
今日から実践できる“断られない電話術”を身につけましょう!
目次
はじめに|「電話営業=テレアポ」の誤解を解くことが第一歩

電話営業と聞くと、「強引」「しつこい」といったマイナスの印象を持つ方も少なくありません。
しかし、保険営業における電話の本来の役割は「契約を迫ること」ではなく、既存顧客との信頼を積み上げることにあります。
ここでは、まず「誤解を正す」ことからスタートしましょう。
誤解しやすい「電話営業」と「テレアポ」の違い
テレアポとは、見込みのない不特定多数に架電して契約を勧誘する行為を指します。一方で、保険業界ではこの手法は金融庁の監督指針により原則禁止です。
これに対し、顧客フォロー電話は「契約後の確認」「問い合わせ対応」「紹介フォロー」など、顧客起点の連絡手段として適正な業務範囲に含まれます。
この違いを理解するだけで、営業の姿勢は180度変わります。
保険営業マンが電話を使う本当の目的とは
目的は「売る」ことではなく、顧客との接触頻度を最適化して信頼を維持することです。
契約後に何度も接点を持つことで、顧客の満足度が上がり、紹介の可能性も高まります。
実際、MDRT会員の多くが「契約後フォロー」を最も重要視しています。
この記事で得られる3つの実践スキル(信頼・フォロー・紹介)
-1024x559.jpg)
現場ですぐに再現できる、3つの重要ポイントを押さえていきましょう。
1.法令に抵触せず、顧客満足度を上げる電話活用法
金融庁の監督指針を踏まえたうえで、“売る電話”ではなく“助ける電話”を設計します。
手続き案内や契約内容確認など、顧客にとって有益な目的でかけるだけで、信頼が自然に積み上がります。
結果的に、解約防止や紹介増加にもつながる“法令順守型コミュニケーション”が身につきます。
2.心理学に基づく「断られにくい」トーク設計
トークのコツは、説得ではなく共感と質問です。「はい・いいえ」で終わらない質問を投げかけ、相手の考えを引き出すことで、押し売り感を消しながら関心を高めます。
心理的距離を縮める“安心感の演出”が、次の面談や紹介の糸口を生みます。
3.電話後フォローを軸にした紹介・リピート戦略
成約直後や手続き完了後の“アフターコール”は、最も信頼を育てやすい瞬間です。短い一言フォローを積み重ねるだけで、「この人は忘れない担当者」という印象を形成できます。
その積み重ねが、リピート・紹介・口コミという長期成果に変わっていきます。
保険営業で電話を使う前に知っておくべき基本と注意点

どれだけトーク力があっても、ルールを理解せずに電話営業を行うのは危険です。ここでは、法的な前提と実務での線引きを整理しましょう。
保険業法・金融庁ガイドラインが定める禁止行為
保険営業で電話を活用する際には、まず法令上のルールを理解することが大前提です。
保険業法および金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」では、顧客の意向を把握せずに行う電話勧誘や、同意のない再架電などは適正な募集行為に該当しないと明示されています。
また、虚偽説明・誤認を与える表現・威圧的な対応は、いずれも不適切募集として各社のコンプライアンス規程でも厳しく制限されています。
そのため、電話をかける際は「相手が求めている情報を届けること」や「既存契約の確認・案内」に目的を絞ることが重要です。
営業担当者が守るべきなのは「数をかけること」ではなく、“顧客にとって意味のある電話”を行うことです。
これが結果的に法令順守と信頼向上の両立につながります。
※出典:金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」第Ⅳ-2-1-2(3)など
※本記事の内容は、法令の一般的な要点を解説したものであり、特定の法的判断を示すものではありません。
「テレアポ」と「顧客フォロー電話」の境界線
フォロー電話は、顧客がすでに「関係を持つ」相手である点が決定的に異なります。
問い合わせや資料請求、既契約など、相手の同意や期待が前提にある場合には、連絡の意義があります。
逆に、名簿購入などで得た電話番号に無作為にかけるのはコンプラ違反のリスクが極めて高いと理解してください。
目的を“販売”から“サポート”に変えることで成果が安定する
顧客にとって「助かる電話」であれば、拒絶反応は起きません。たとえば、給付金請求や控除証明書の時期に「確認と案内」を行うだけで信頼度は上がります。
“売らない会話”こそが、次の商談の扉を開く最短ルートです。
既存顧客・紹介顧客への電話フォローで信頼を深める方法

信頼構築の鍵は「適切なタイミング」と「相手中心の会話設計」にあります。
契約後のフォローが解約防止と紹介拡大を生む理由
契約直後や給付申請後、更新前のフォローは、顧客との関係を維持・強化する重要なタイミングです。
フォローの目的は「販売」ではなく、「契約内容や手続きを安心して理解してもらうこと」その積み重ねが、結果として信頼の維持や顧客ロイヤルティ向上につながります。
多くの保険会社では、定期的なアフターフォロー体制を設け、手続き確認や制度改定の案内を通じて、顧客が安心して契約を継続できるようサポートしています。
実務の現場でも、こうした“顧客目線のフォロー”を続ける担当者ほど、解約率が低く、紹介が生まれやすいという傾向が報告されています。
話し方・時間帯・頻度で信頼度が変わる|実践チェックリスト
電話で大切なのは「何を話すか」よりも「どう伝えるか」です。トーン・タイミング・頻度の3点を意識するだけで、相手の受け取り方は大きく変わります。
トーン:落ち着いた低めの声で、ゆっくり・はっきり話す
→ 急ぎすぎる話し方は“売り込み感”を与えるため、安心感を重視したテンポが理想です。
時間帯:平日17時以降や休日の午前中は応答率が比較的高い
→ 勤務や家事が一段落した時間帯にかけることで、相手の心理的余裕を得やすくなります。
頻度:年3〜4回の定期フォローに加え、手続きや更新期日前に1回追加
→ 「思い出したタイミングで連絡」ではなく、年間計画としてフォローを組み込むのが効果的です。
さらに、CRM(顧客管理ツール)で連絡履歴を残しておくと、「前回どんな話をしたか」「どんな時期に反応が良かったか」といった顧客ごとの“温度感”が可視化されます。
この記録が、“かけどき”を逃さない信頼維持の仕組みになります。
紹介が自然に増える会話フレーズと成功例
紹介を増やしたいときほど、直接「紹介してください」とは言わないのが鉄則です。人は“頼まれた”よりも“思い出した”ときに動くため、共感ベースの一言が効果を発揮します。
たとえば、
「同じように手続きで困っている方がいたら、私のことを思い出してください。」
この言葉は、相手に負担をかけず、紹介を“任意の行動”として促す心理的な仕掛けです。
実際の現場でも、契約後や給付完了後などのタイミングでこの一言を添えると、「そういえば、知り合いに保険で悩んでいる人がいる」と自然に話題が広がるケースが多く見られます。
大切なのは、感謝と余韻で終わる会話にすることです。売り込みではなく“信頼の余白”を残すことで、紹介は無理なく生まれます。
断られにくい電話トークの作り方|心理学と営業科学の融合

成果を左右するのは「最初の30秒」です。ここでは心理学を活かした会話術を紹介します。
第一声で安心感を与える「声のテンポ・間・言葉選び」
第一声で名乗り→目的を簡潔に→相手の都合を確認します。この3ステップを15秒以内で終えるのが理想です。
声は低くゆっくりを心がけましょう。間を恐れず、相手が考える余地を残します。心理学的に“間”は信頼形成のサインとして機能します。
オープンクエスチョンとイエスセットで信頼を積み上げる
「どの点がご不安でしたか?」「最近、ご家族の保険を見直されましたか?」このように、Yes/Noでは答えられない質問で相手の話量を増やすのがポイントです。
その後に「そうですよね」「たしかに」と共感+要約を挟むと信頼感が増します。
断られても関係が続く“再アプローチトーク”の型
断られたときこそ、印象を決める大切な瞬間です。無理に押したり、すぐに切り上げたりせず、相手の状況を尊重しながら温かく締めくくることが、次のチャンスを生みます。
「今日はお話を伺えてうれしかったです。今はご都合のタイミングではないと思いますが、また何かあったときは気軽にご相談くださいね。」
このように感謝と余白を残す終わり方をすると、相手の中に「この人は感じが良い」「また話してもいいかも」という印象が残ります。
短いやり取りでも誠実さが伝われば、将来的な再アプローチの糸口につながります。
成約後・面談後の“電話後フォロー”で信頼を資産化する

フォロー電話は、言い換えれば「顧客関係を再起動するボタン」です。
特に、面談や手続きが終わった直後のフォローは、相手の記憶に残りやすく、信頼を深める絶好のタイミングです。
面談後48時間以内に「お時間をいただきありがとうございました」と一言添えるだけでも、「きちんと対応してくれる担当者」という印象を残すことができます。
この小さな積み重ねが、次の相談・紹介・契約更新につながる“関係資産”を築きます。
フォロー電話の最適タイミングと成功率の関係
フォローの目的は「思い出してもらう」ことではなく、信頼を“継続中の関係”として感じてもらうことです。
反応が良いのは、顧客の記憶に担当者がまだ残っている時期、つまり「面談の翌日」「手続き完了の翌日」「年末調整や保険料控除の時期」です。
電話は長く話す必要はありません。「感謝 → 要点確認 → 補足説明 → 一言フォロー」この4ステップで十分です。
たとえば、
「先日はお時間をいただきありがとうございました。手続きの件、無事に進んでおります。ご不明点などはございませんか?また何かあればいつでもご連絡くださいね。」
こうした短い一言が、“誠実に対応してくれる人”という印象を残し、次の紹介や契約更新のきっかけになります。
CRM活用でリピートと紹介を自動的に生み出す仕組み
フォローを継続できない営業マンの多くは、“誰に・いつ・何を話したか”を覚えていないことが原因です。
CRM(顧客管理ツール)に通話内容や感情のメモを残すだけで、次の最適な話題やタイミングが明確になります。
たとえば、前回の記録に「お子さんの進学で保険を見直したいと話していた」とあれば、次回の電話でその話題を自然に切り出せます。
「気にかけてくれている」と感じてもらう瞬間が、信頼関係を深める最大のポイントです。
また、CRM上でフォロー周期(例:3か月・半年ごと)を自動設定すれば、“連絡忘れ”が防げるだけでなく、紹介・リピートの機会を逃さない仕組みが作れます。
紹介依頼を自然に行う「一言メッセージ」とその心理効果
紹介を増やすには、“紹介してください”と直接お願いするよりも、相手が「また相談したい」「この人なら紹介してもいい」と感じる関係を作ることが大切です。
「もし同じように手続きでお困りのことがありましたら、またお力になれればと思います。」
この一言は、お願いではなく“気遣いの延長”として受け取られます。
相手に行動を求めるのではなく、信頼の余白を残す言葉だからこそ、自然な形で再相談や紹介が生まれやすくなるのです。
法令遵守と信頼維持のために避けるべきNG電話対応

どんなに営業力が高くても、法令や倫理を欠いた対応は信頼を一瞬で失うリスクがあります。
ここでは、金融庁が定めるルールや実務で起こりがちな“NG対応”を整理しながら、保険営業として信頼と成果を両立させるポイントを解説します。
強引な勧誘・誤解を招く表現の具体例
電話営業で最も避けるべきは、顧客の不安を煽ったり、誤解を与える表現です。
たとえば、
「今入らないと損しますよ。」
「この商品は今月で終了します。」
といった言葉は、一見セールストークのように聞こえますが、実際には誇大広告や不当勧誘に該当するおそれがあります。
顧客は「自分の利益より契約を優先された」と感じた瞬間に心を閉ざします。保険営業における信頼は、一度失うと取り戻すのが難しいものです。
短期的な成果を狙うより、顧客の理解と納得を積み重ねる姿勢が結果的に紹介・リピートを生みます。
金融庁が明示する「電話募集でやってはいけないこと」
金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」(Ⅱ-4-2-1~Ⅱ-4-2-2等)では、電話による勧誘に関して以下の行為を明確に禁止しています。
1.顧客の意向を把握せずに勧誘すること
2.必要な説明を行わないこと
3.断りを受けたにもかかわらず再度架電すること
4.事実と異なる説明を行うこと
とくに「一度断られた後の再アプローチ」は、監督指針上でも不適切行為として明記されています。
多くの保険会社が募集人規程やコンプライアンス研修でこの点を最重要項目に位置付けているのはそのためです。
※参考:金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」第Ⅱ-4-2-1~Ⅱ-4-2-2より
コンプライアンスを守りながら成果を上げる3原則
法令を守ることは目的ではなく、信頼を積み上げるための前提条件です。成果を出す営業ほど、この基本を徹底しています。
1.顧客の都合を最優先する
相手の生活リズムや状況を尊重し、連絡のタイミングを調整する。
2.情報提供を目的とし、販売は結果とする
“売るための電話”ではなく、“伝えるための電話”を心がける。結果的に、販売が自然に後からついてきます。
3.記録・再確認を怠らない
通話内容や要点を記録することで、説明責任を果たすと同時にトラブルを防げます。
これらは法令で定められたルールではなく、実務の中で確立された“営業の基本原則”です。
金融庁の監督指針が求める「顧客本位の業務運営」に沿って行動することで、結果的に信頼と成果の両立が可能になります。
よくある質問(FAQ)|保険営業マンが電話活用で迷いやすいポイント
|保険営業マンが電話活用で迷いやすいポイント-1024x585.jpg)
電話対応に関する疑問は、保険営業マンの多くが共通して抱えるテーマです。
ここでは、法令遵守の観点と営業実務の観点の両面から、よくある質問に答えていきます。
金融庁の監督指針で定められている事項と、現場での実践ノウハウを混同しないように注意しましょう。
Q1.テレアポとフォロー電話の違いをどう説明すればいい?
最も大きな違いは、「相手との関係性」と「目的」にあります。
フォロー電話は、すでに契約や面談を行った顧客に対して行うサポート目的の連絡です。
契約内容の確認や、給付・更新・制度改定の案内など、顧客の利益につながる情報提供が目的です。
一方で、テレアポ(電話勧誘)は、顧客の同意を得ないまま不特定多数に対して行う新規営業活動を指します。
これは保険業法および金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」(Ⅱ-4-2-2「募集上の留意点」)で不適切な勧誘行為とされています。
Q2. 紹介電話の最適な頻度は?
紹介電話の頻度は、「数」よりも「タイミングと内容の質」が重要です。
顧客にとって意味のある情報を届けられるタイミングで連絡を入れるのが望ましいでしょう。
たとえば、保険料控除・給付申請・更新案内の時期などは、自然に連絡を入れやすい時期です。
「ご負担をおかけしないタイミングで」「役立つ情報をお届けする」という姿勢を貫くことが、紹介につながる信頼構築の第一歩です。
※この項目は法令による義務ではなく、営業実務における推奨基準としての目安です。頻度よりも“顧客の関心や状況に合わせて話す”ことが成果を左右します。
Q3. 電話内容は録音・記録が必要?
はい。特に契約内容の説明や意向確認に関わる通話は、録音や要点記録を残しておくことが推奨されます。
万一のトラブルが起きた際の証拠としてだけでなく、顧客対応の品質向上にも役立ちます。
多くの保険会社では、CRM(顧客管理システム)や社内記録ツールを用いて、「いつ・誰に・どんな話をしたか」を整理・保存することを義務または推奨しています。
信頼を守るポイント
録音・記録は“自己防衛”ではなく“顧客保護”のために行いましょう。記録を残すことで、再連絡時にスムーズにフォローできます。
※参考:金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」Ⅱ-4-2-1(適正な保険募集管理態勢の確立)
まとめ|電話を“営業ツール”ではなく“信頼を育てる資産”に変える
電話営業の本質は「販売」ではなく「関係」です。法令を守り、誠実に対応することこそが最も効果的な営業戦略です。
顧客の利益を最優先に考える姿勢は、やがて紹介・リピート・安定収入へとつながります。
今日から、「1本の電話で1つ信頼を積む」意識で取り組みましょう。それが、MDRTを目指す保険営業マンにとっての最短ルートです。