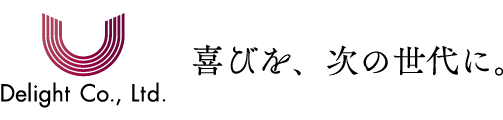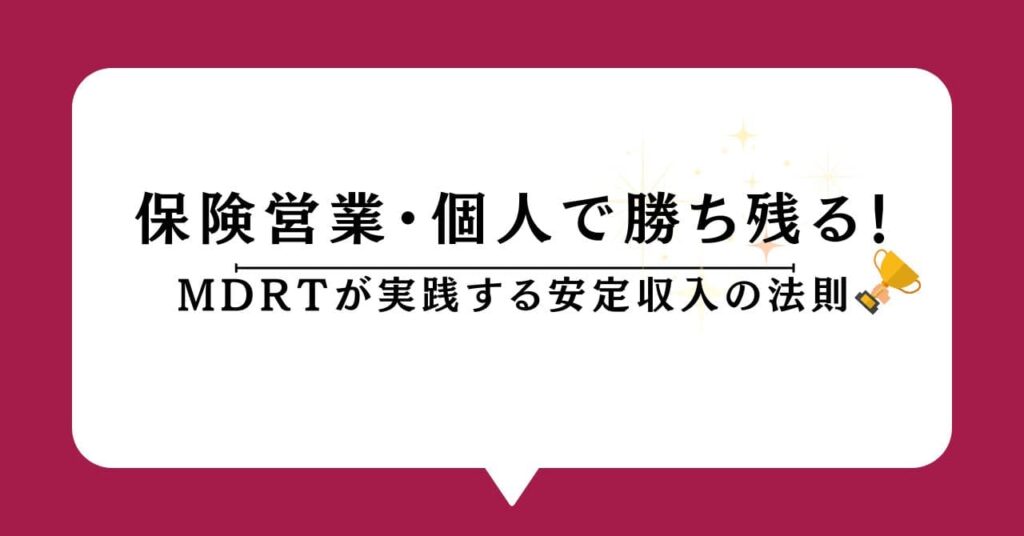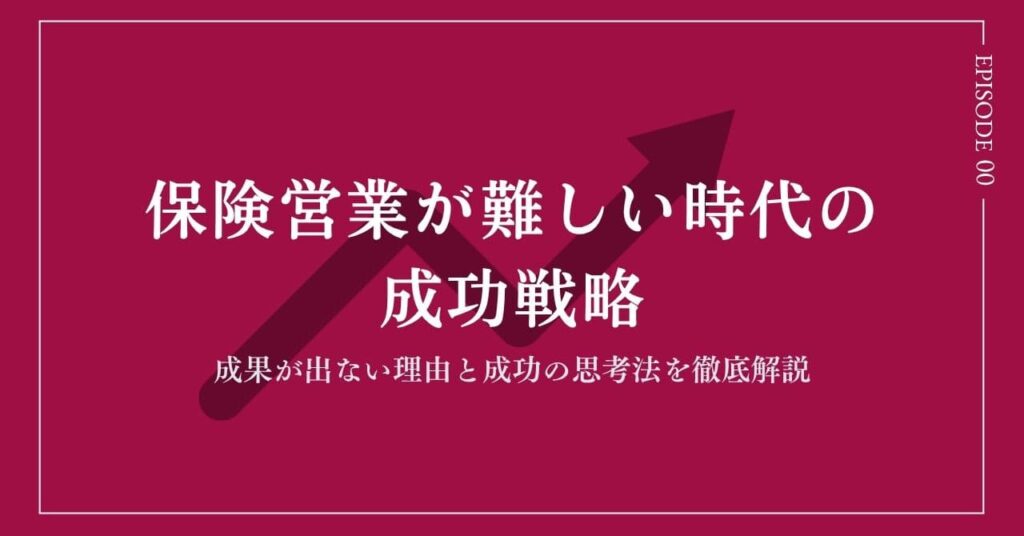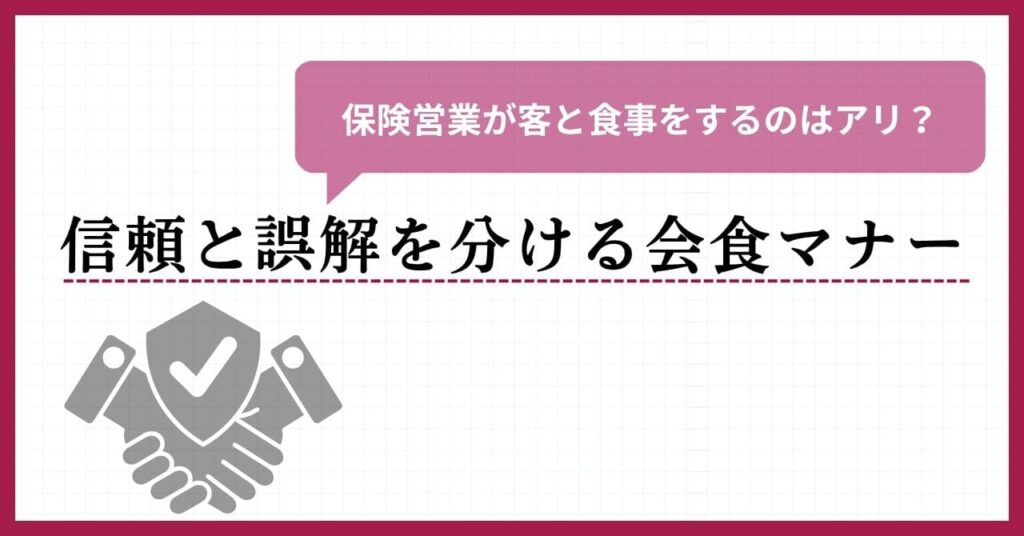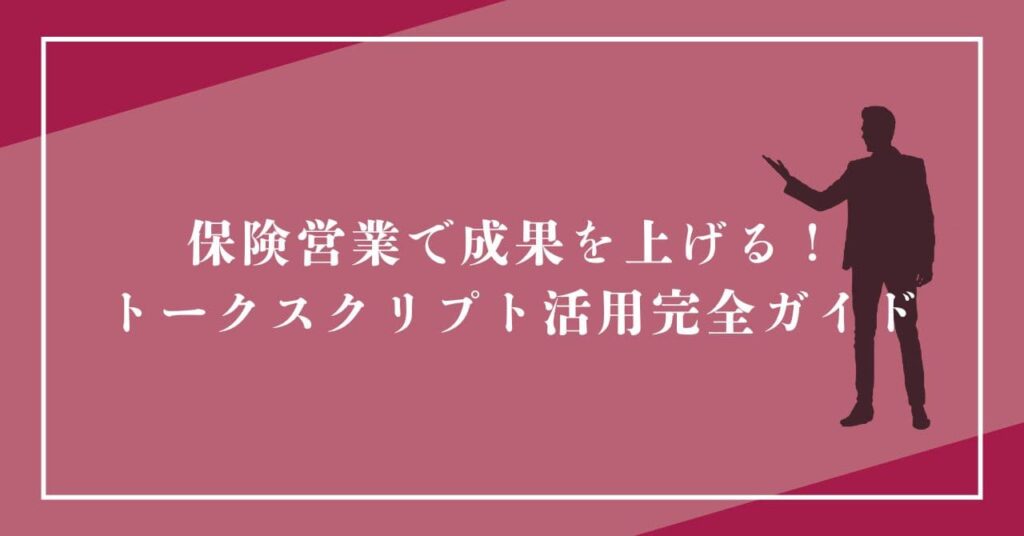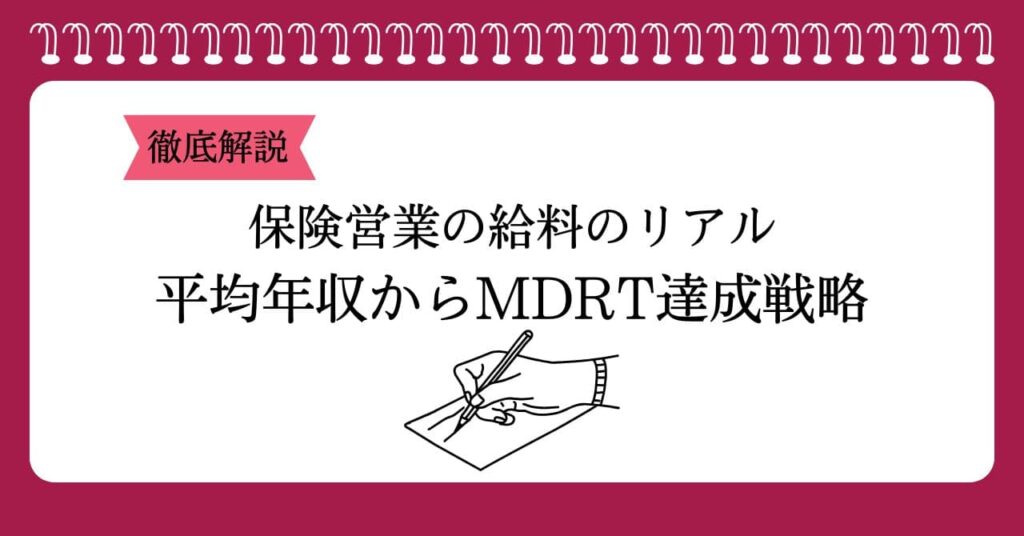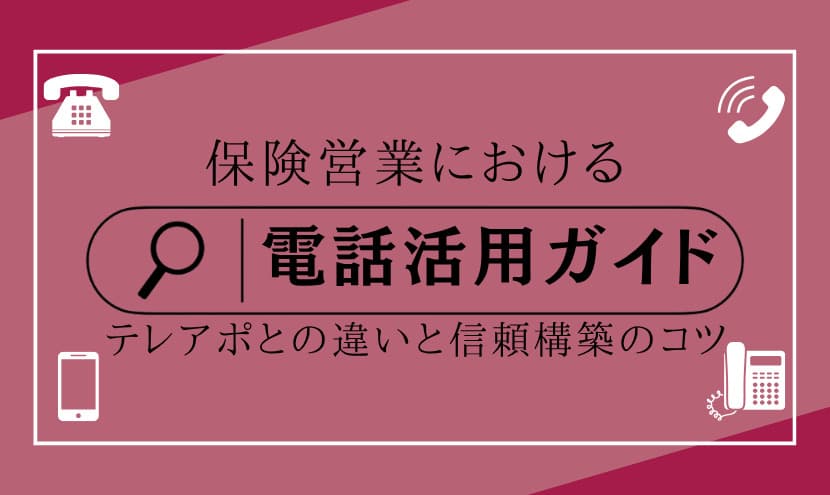保険営業フリーランスで年収の壁を超える!MDRTを目指すための独立・働き方・高単価案件獲得ガイド

「このまま会社員のままでいいのだろうか?」保険営業の現場で働く多くの営業マンが、報酬・自由度・将来性の面で悩みを抱えています。
そんな中、「フリーランス保険営業」や「代理店独立」という新しい選択肢に注目が集まっています。
本記事では、保険営業のフリーランス化をめぐる仕組み・手続き・リスク、そしてMDRTクラスの年収を実現する法人営業・事業承継マーケット攻略法までをわかりやすく解説します。
目次
なぜ今、保険営業マンが「フリーランス」を意識し始めているのか
 保険業界では近年、会社に依存せず自分の裁量で働く「フリーランス型営業」が増加しています。
保険業界では近年、会社に依存せず自分の裁量で働く「フリーランス型営業」が増加しています。
その背景には、報酬制度への不満や働き方の制限、そして個人営業中心の限界があります。ここではその理由を3つに分けて整理します。
報酬体系(手数料率)とノルマに対する不満
多くの保険会社では、手数料率が会社主導で決められており、どれだけ成果を上げても上限があります。
さらに、会社の方針やキャンペーンに縛られ、自分の顧客層や得意分野を活かせないことも少なくありません。
「もっと成果に応じた報酬を得たい」という気持ちが、独立への第一歩となります。
働き方・時間・営業スタイルの自由度を求めて
フリーランスになると、勤務時間や営業方法の制限がなくなり、オンライン相談やSNS集客など多様なスタイルを選べます。
たとえば、育児や介護と両立しながら自分のペースで働く営業マンも増加中です。
働き方の自由は、報酬だけでなく「生き方の満足度」に直結します。
個人営業の限界と「年収の壁」への焦り
個人向け保険は競合が激しく、契約単価も限られています。MDRTクラスを目指す営業マンの多くは、より高単価な法人保険・事業承継案件に活路を見出しています。
そのためには会社の制約を超え、より柔軟に商品を扱える立場=フリーランス化が有効なのです。
保険営業の「フリーランス化」とは?3つの代表的な働き方
 一口にフリーランスといっても、働き方にはいくつかの形があります。ここでは代表的な3パターンを解説し、正社員との違いも整理します。
一口にフリーランスといっても、働き方にはいくつかの形があります。ここでは代表的な3パターンを解説し、正社員との違いも整理します。
フルコミッション型(業務委託契約)
フルコミッション型とは、保険会社と業務委託契約を結び、完全歩合制で働くスタイルのことです。
成果がすぐ収入に反映される一方で、固定給や保証はありません。初期補給金制度をうまく利用すれば、独立初期のリスクを抑えられます。
保険代理店としての独立・開業
保険代理店としての独立や開業とは、個人事業主や法人として、自ら保険代理店を開業する方法です。
自分の顧客基盤をもとに、提案スタイルや経営方針を自由に決められるのが強みです。会社員から経営者へのステップアップとして人気が高まっています。
複数社と提携する乗合代理店という選択肢
乗り合い代理店とは、複数の保険会社と提携し、顧客に最適な商品を選べる仕組みです。
「売る」営業から「比較・設計・提案する」コンサルティング営業へと進化できるのが特徴です。法人案件や資産運用提案にも対応しやすく、成長の幅が広がります。
正社員との違い:雇用・報酬・責任の構造
正社員は社会保険・給与保証などが整っている反面、報酬上限や営業エリアに制限があります。
フリーランスは自由度が高い代わりに、確定申告や社会保険などの管理も自己責任です。ただし、この「責任=裁量」が、真のキャリアアップにつながります。
フリーランス保険営業のメリットとデメリット
 独立は夢のある選択肢ですが、メリットとリスクを正しく理解しておくことが成功のカギです。
独立は夢のある選択肢ですが、メリットとリスクを正しく理解しておくことが成功のカギです。
青天井の年収・成果連動のやりがい
努力した分だけ報酬が増えるのが最大の魅力です。固定給では到達できない収入ゾーンに手が届きます。
特に法人案件を獲得できれば、1件で数十万円〜数百万円の報酬も現実です。
顧客本位の提案ができる自由
複数社の商品を扱えるため、顧客に本当に合ったプランを提案できます。
「売り手」ではなく「顧客の伴走者」として信頼される営業スタイルが築けます。
社会保険・安定収入を失うリスク
会社が半分負担してくれていた保険料をすべて自己負担する必要があります。
また、月による収入変動も大きく、生活防衛資金を確保しておくことが必須です。
孤独・自己管理・学び続ける力が必要
誰も営業計画を立ててくれません。目標設定・顧客管理・スキルアップすべてが自己責任です。
フリーランス成功者の多くは、常にセミナーや勉強会に参加し、最新知識を学び続けています。
独立前に知っておきたい準備と手続きの全体像

独立は勢いだけでは成功しません。ここでは、実際に独立する際に必要な手続きと準備をステップごとに紹介します。
開業届・青色申告承認申請書の提出
税務署への開業届提出は必須です。青色申告を選ぶことで、最大65万円の控除が受けられ、節税効果も高まります。開業届は退職後1カ月以内の提出が理想です。
国民年金・健康保険への切り替え
退職後は社会保険から国民健康保険・国民年金へ切り替えます。
任意継続よりも長期的には負担軽減になる場合もあるため、シミュレーションして最適な選択をしてください。
代理店契約・募集人資格の登録
どの保険会社・代理店と提携するかは、収入や働き方に大きく影響します。
募集人資格の維持やコンプライアンス研修の受講も忘れずに行いましょう。
初期費用・営業ツール・オフィス準備
名刺・CRMツール・HP制作などの初期投資は10〜30万円が目安です。
オンライン相談を取り入れるなら、照明・カメラなども整えておくと印象が格段に上がります。
独立1年目でつまずかない!確定申告と経費管理のポイント

独立後、多くの方が悩むのが「お金の管理」です。帳簿・税金・社会保険を整理しておくことで、後から慌てずに済みます。
青色申告のメリットと手続き
青色申告では、経費の計上と特別控除で税負担を軽減できます。
クラウド会計ソフトを活用すれば、簿記の知識がなくても自動で仕訳が可能です。
経費計上できる主な費用
交通費、通信費、広告費、会議費、事務所家賃、書籍代などが対象です。
特に顧客との打ち合わせに使う飲食費は50%までが経費として認められます。
「家内労働者等の必要経費の特例」を理解する
保険外交員などの一部業務委託者には、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用される場合があります。
この制度を利用すれば、実際の経費が少なくても一定額を必要経費として認めてもらえるため、帳簿付けや領収書整理の負担を減らせます。
たとえば、令和6年(2024年)時点では上限55万円までが特例として認められています。
実際の支出が55万円未満でも、その金額を必要経費として計上できるため、確定申告が格段にスムーズになります。
詳細な条件や申請方法については、国税庁の公式ページを参照してください。
参考:国税庁「No.1810 家内労働者等の必要経費の特例」
税金・社会保険の負担を軽減する方法
iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済は、掛金の全額が所得控除の対象となるため、フリーランス保険営業にとって代表的な節税制度です。
たとえば、iDeCoは月最大6.8万円(年81.6万円)、小規模企業共済は月最大7万円(年84万円)まで拠出でき、節税と老後資金づくりを同時に実現できます。
具体的な上限額や申請手続きは、国税庁・中小機構・iDeCo公式サイトで最新情報を確認しましょう。
成功するフリーランス保険営業の共通点と失敗パターン

フリーランスで成功する人と、苦戦する人には明確な違いがあります。
その差は「売り方」ではなく、「市場選び」と「学び方」にあります。
失敗パターン:個人営業中心の消耗型モデル
フリーランス独立後に多いのが、「売り方」・「市場選び」・「学び方」すべてが個人保険中心に偏ったままのケースです。
| 売り方 | 個人のリスクに備えた保険提案 |
| 市場選び | 個人客中心で契約単価が低い |
| 学び方 | 経験頼みや属人的ノウハウに依存 |
売り方では、友人・家族・紹介頼みの営業を続け、価格競争に巻き込まれがち、値引きやキャンペーン依存で利益率が低下し、成約しても継続率が伸びません。
市場選びも、個人客中心だと契約単価が低く、常に新規獲得プレッシャーに晒されます。
独立直後ほど「安定収入」を求めて低単価案件に偏りやすく、結果的に疲弊してしまうのです。
さらに学び方の面でも、経験頼みや属人的ノウハウに依存し、体系的な知識アップデートを怠る傾向があります。
税務・相続・法人経営の知識が不足すると、高単価提案のチャンスを逃すことになります。
成功パターン:法人・事業承継マーケットを攻略
一方、MDRT達成者に多いのは、「売り方」「市場選び」「学び方」を戦略的に設計しているタイプです。
| 売り方 | 経営者の課題解決に備えた保険提案 |
| 市場選び | 経営者中心で契約単価が高い |
| 学び方 | 経営者支援に携わる知識を継続的に学習 |
売り方では、単なる保険販売ではなく、経営者の課題をヒアリングし、保険を“解決策の一部”として提示します。
商品の提案ではなく、「財務・事業承継・福利厚生」の改善提案を行うことで、信頼と高単価契約の両立を実現しています。
市場選びでは、法人・事業承継・医療法人などの“経営課題を持つ顧客層”を狙い、1件あたりの契約価値を最大化しましょう。
成約後は、同業種ネットワークや顧問税理士経由の紹介により、リピート・紹介率も高まります。
学び方では、税制改正・法人保険・財務設計など、経営者支援に必要な専門知識を継続的に学んでいます。
学習は単発セミナーではなく、体系的にアップデートを続けることで“提案の深み”が増していきます。
MDRT達成者に共通する「学び」と「仕組み化」
トップ営業マンに共通するのは、「学びを仕組み化して再現性を高める」姿勢です。
たとえば、以下の3つの要素を実践している人が多く見られます。
1.学びの仕組み化
業界・税制・法人保険の最新情報を週単位でインプット。
独学ではなく、専門講座や事業承継セミナーなどで体系的に学ぶことで、提案の幅を常にアップデートしています。
2.営業プロセスの見える化
CRM(顧客管理システム)を活用して、アプローチ・ヒアリング・契約・フォローを数値で管理。
「どの提案が成約につながったか」「次に改善すべきポイントは何か」を可視化しています。
3.再現可能な提案モデルの構築
顧客ごとに異なるニーズを“設計テンプレート化”し、提案書や面談スクリプトを共有・改善。
属人的な営業から脱却し、安定した成果を生み出す「再現性のある営業体制」を作り上げています。
このように、MDRT達成者は「学び方」「仕組み」「提案手順」の3点をシステムとして運用しています。
その積み重ねこそが、年収・契約数・信頼のすべてを持続的に伸ばす最大の要因です。
高単価を実現する「事業承継営業」という新しい武器

独立後に最も成果を上げているのが「事業承継営業」です。これは単なる保険販売ではなく、企業の未来を設計するコンサルティング型の営業手法です。
なぜ事業承継案件は高報酬につながるのか
法人保険は1件あたりの契約金額が大きく、報酬も高水準です。さらに、経営者との長期的関係が築けるため、継続収入のベースになります。
経営者に信頼される提案プロセス
財務・税務・人事などの全体像を把握し、保険を「手段」として提案することが大切です。
表面的な説明ではなく、数字に基づいた根拠ある提案が求められます。
実践で学ぶ「事業承継×保険」の成功モデル
成功者の多くは、体系的な研修で知識と実例を学び、提案スキームを確立しています。
法人営業は経験だけでは習得できず、「理論×実践」の両輪が必要です。
【セミナー案内】事業承継ノウハウを体系的に学ぶ無料講座のご案内
もし「法人開拓に挑戦したい」「MDRTクラスの提案力を磨きたい」と思う方は、事業承継セミナーの受講がおすすめです。
経営者との関係構築や高単価提案の実例を学べる無料講座もあり、フリーランス営業として次のステージへ進む最短ルートとなるでしょう。
まとめ|「自由×高収入×信頼関係」を実現するキャリアへ

フリーランス保険営業は、「自由な働き方」「高単価案件」「顧客との長期信頼関係」をすべて両立できる新しいキャリアモデルです。
ただし、成功の鍵は「知識・仕組み・学びの継続」にあります。
高単価ノウハウと学びの環境がMDRTへの最短ルート
個人の努力だけでなく、正しい情報源と学びの環境を選ぶことが重要です。
もし「法人開拓に挑戦したい」「MDRTクラスの提案力を磨きたい」と思う方は、事業承継セミナーの受講がおすすめです。
事業承継や法人営業の知識を体系的に学び続ければ、MDRTも夢ではありません。
独立後も“学び続ける営業”として、自らの可能性を最大化していきましょう。
より実践的な学びや、法人向け提案支援の具体事例を知りたい方は、こちらも参考にしてください。